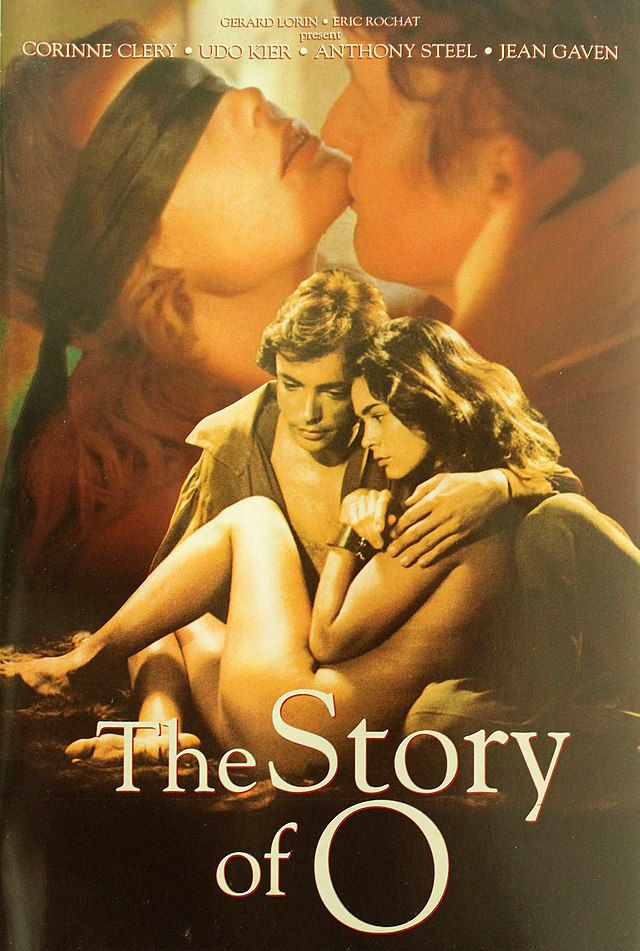【ワインカントリー】アメ車のなかの男と女と女
- 香月葉子

- 2022年3月6日
- 読了時間: 2分
更新日:1月2日
助手席の窓をあけて、暮れてゆくカリフォルニアの空をながめていた。
目をあけられないほどの強さで顔を打ちたたく風が心地よかった。
このまま頭もろとも吹きとばされてしまえばいいのにと願っていたのかもしれない。
緒斗(おと)はステアリングウィールをにぎったまま、もういっぽうの手をわたしのひざにおいていた。
「時速80マイルだから、いま時速120キロは超えてるってことか。さすがに8気筒だね。軽く踏んでるだけなのに」
「静かだから60キロくらいで走ってるのかと思ってた」とわたし。
「そろそろ、窓、閉めたら?」と彼
「もうすこし、こうしていたい」
「風の音がうるさいだろ?」
「Yoko、わたしは気にしないから」と後部座席からリヴが言った。
「え? 彼女、なんだって?」と彼は声を強めた。
「わたしはうしろでもっともっと風をあびていたいな、て言ったの」
そう叫んだリヴは、後部座席から手をのばし、緒斗の髪の毛をかきまわしたあと、こんどはわたしの首に背後から腕をまきつけて耳たぶにくちづけしてきた。
その唇の感触が、いまでも、ふいに、もどってくることがある。
「今夜はどうする? モーテル?」と緒斗。
「サンタローザの町のなかで泊まるのは大変だと思う」とわたし。
「さがすのは面倒だし、カネもかかるしなぁ」
「サンタローザをちょっとすぎたらモーテルが見つかるわよ」とリヴ。
1974年型の白いフォードLTD の車内でのことだった。
病院の待合室のベンチみたいに切れ目のない大きな硬いシートが大好きだった。
緒斗とのあいだにアームレストもないので体をくっつけるのが楽だった。
バークレーで出会った在日韓国人の留学生チョーさんから1500ドルで手にいれたものだ。
彼に現金を手わたして、必要書類をオークランドにあったカリフォルニア州車両管理局 (Department of Motor Vehicles) に提出して、それで終わりだった。
アメリカにきたのだと感じた。
1981年 春 / サンタローザへ向かう101号線
無断引用および無断転載はお断りいたします
All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko
All Rights Reserved.