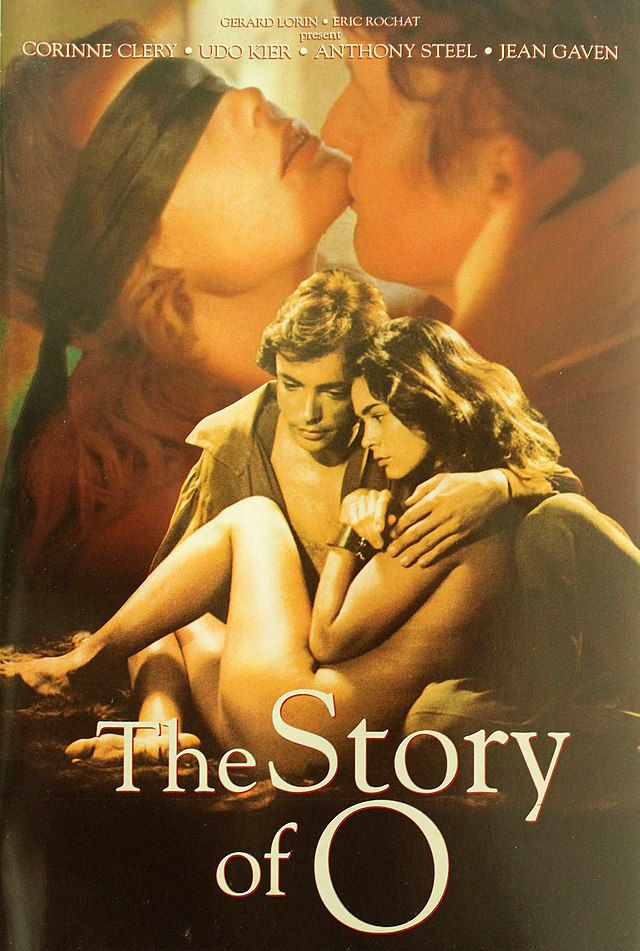異人種間結婚の夢 | 帰国当日に「別れ」を告げられて
- 香月葉子

- 2024年5月13日
- 読了時間: 9分
更新日:7 日前

大阪国際空港から離陸したサンフランシスコ行きノースウェスト航空(2010年以降はデルタ航空に統合されました)の旅客機のキャビンには乾燥したクリーンな空気が満ちていた。
夜だったけれども、雲海のひろがりが目に入る高さにまで上昇したあとは、角の丸い旅客機の窓に目をむけるたびに、澄みわたった夜空を見ることができた。けれども飛行機が苦手だったわたしは、ドリンクサービスを受けたあとも、通路側の席に腰かけたまま、自分の鼓動を鎮めるために、あまり窓のほうは見ないようにしていたような気がする。
緒斗(おと)も通路側だったけれど、わたしのすぐ真うしろの席で、ふたりは離れ離れだった。

となりに腰かけていた黒人青年がわたしの顔を覗きこむようにして声をかけてきた。
彼は出発時間ギリギリにキャビンへ駆けこんできた青年だ。
20代半ばに見えた。
英語で話しかけてきたのはわかったのだけれども、発音に独特の訛り(なまり)があるため、聞き取るのがむつかしかった。
「きみ、顔色が悪いようだけど、気分でも悪いのかい?」
「だいじょうぶです。ただ、飛行機が苦手なだけだから」
「怖いんだね。おれも好きじゃないよ。落ちたら、それまでだしね」
「助かる可能性がゼロだからスッキリしてていいかもしれない、て言う人もいるけど」
「だろ? 運を天にまかせて、てことさ」
「でも…わたしたちの場合、天ではなくて、パイロットさんに命をあずけてるわけでしょ?」
「まあね」
「そこのところが、なんとなくスッキリしなくて…」
「しかたがないよ。だれかが操縦してくれないと、こいつ、飛ばないからな」
「でも、なにかあったとき、あきらめがつかない、ていうか。ただ、ぐうぜんにも、この便のこの飛行機のこのパイロットになったのが運が悪かった、てことになって…」
「そりゃ、まぁ、知り合いのクルマに乗ってるのとはちがうよな」
「知り合いのクルマだったら、わたしの選んだことだから、しかたがないって、なんとなくあきらめがつくけど」
「うん。きみが言いたいこと、なんとなくわかるよ」
「よかった」
「おれだって、まったく知らないやつに自分の命をあずけるのはごめんだな。信用できないやつのヘリには乗りたくないもんな」

そして彼は笑った。歯の白さが目立った。これほど身近に黒人を見たのは初めてだった。しかも見惚れてしまうほど、ローストされたコーヒー豆のような肌に、凛々しい美しい顔立ちをしていた。頭が小さく、手足が長く、指はとくに長く、整った筋肉質の体つきで、もしかしたら彼の先祖はエチオピア人かソマリ族だったのかもしれないとおもわせるような、どちらかといえば白人に近い顔つきで、鼻すじは通っていて、髪の毛もそれほどちぢれ毛ではなく、かなり上背があった。
ついこのあいだまで、アフリカの戦士だったと言われても、信じてしまったかも知れない。

「アメリカへは、旅行?」と彼。
「ううん、カリフォルニア大学バークレー校帰属の英語学校に入ることになってるの」
「てことは、けっこう長く滞在するわけ?」
「たぶん」
「てことは、とうぜん、往復航空券じゃないってこと?」
「片道です」
「だけど、片道航空券でアメリカに入国できるのかい?」
「日本にいるときに、F1ヴィザは取ってたから」
「F1ヴィザ?」
「学生ヴィザのこと」
「へぇ、そうなんだ。だったらOKなんだ」
「はじめまして、わたし、Yoko」
「おれは」と言いかけた彼のことばを、わたしは「ジェームズさんでしょ?」とさえぎって、彼のベルボトムジーンズの右の膝から裾にかけて大きく縦に刺繍されていた文字を指さした。
『ジェームズ』というカタカナ文字だった。
「なんだ、気がついてたんだ」
「日本人だもの。ジェームズさんは、日本には長かったの?」
「Okinawaにいたんだ。ただ、いつも仲間とばかりいっしょに出歩いてたから、たいして日本語は学ばなかった。あまりうまくないんだ。惜しいことをしたよ」
「Okinawa? もしかして、ジェームズさんは兵隊さん?」
「海兵隊さ。除隊して、これから、テキサスにもどるところなんだ。サンフランシスコでちょっと一泊するけどね」
「じゃ、もう、自由なのね」
「うん、そうだよ。『James-san』は、ようやく自由になったってわけさ」
「おめでとう」
「ありがとう。きみたち、カップルなんだろ?」と彼は首を後部座席にまわして緒斗を見た。

そして「窓側の席は空いてるから、こっちにきたらいいじゃないか」と言うなり緒斗に声をかけようとしたので、わたしは急いでそれをとめた。
「でも、誰かの席かもしれないわ。ハワイに寄ったときに、誰かが乗ってくるかもしれないし」
「いや、もう、誰も来やしないよ」
「え? どうして?」
「じつはおれの彼女の席だったんだ。一緒に搭乗するはずだったんだけど、けっきょく来なかったから、アメリカまでずっと空席のはずだよ」
彼は残念そうな表情でコトバをにごすようにつぶやいた。
なにか事情がありそうな気がして、わたしは少し気まずい思いがしたので、背後をふりむいて、こちらの席へ移ってもだいじょうぶみたいだと緒斗に伝えたあと、ジェームズに感謝の言葉をつたえた。

ジェームズは通路側を望んだので、緒斗が真ん中の席にすわることになり、わたしは窓側に移った。彼のおかげで、サンフランシスコまで、緒斗とずっと肩を触れあわせる距離で食事と会話を楽しむことができるようになったのがうれしかった。
食事のあと、わたしは窓に頭をあずけ、目を閉じたまま、ジェームズと緒斗の会話に耳を傾けていた。

一緒に搭乗するはずだった彼の恋人はマリコという名前だった。
R&B(リズム&ブルーズ)とスノーケリングが大好きなマリコさんは、ブティック勤めの24歳で、ジーンズに刺繍されたカタカナの『ジェームズ』は彼女の作品だったらしい。
ふたりは沖縄の那覇市で知り合ってデートするようになり、気づいたときには結婚を前提にした付き合いに変わっていた。
『いつかサンフランシスコという街を見てみたい』と言っていたマリコさんのために、彼はサンフランシスコの中心街にあるホテルの部屋を予約していた。
そこで一泊したあとにテキサスに住む彼の両親に会わせるつもりだったと言う。

マリコさんは那覇市のブティックで働いていたが、実家は大阪にあり、渡米する前に両親と過ごすため、彼より先に沖縄を離れていた。
そしてジェームズのほうは、二人分の航空券をもって大阪国際空港の待ち合わせの場所に行ったのだけれども、彼女は姿をあらわさなかった。
公衆電話から彼女の実家に電話をかけると『ハロー』と言った瞬間に電話を切られたのだそうだ。それでも彼はあきらめずになんどか電話をかけてギリギリの時間まで待ち続けたけれども、彼女の声すら聞けないまま、あきらめて、この便に搭乗してきたのだった。
「きっと両親から反対されたんだな。おれのほうの親は日本人の恋人を連れて帰るって伝えたら、電話がぶっこわれるくらいに大声で喜んでくれて、彼女に会えるのを楽しみにしていたのに。おれ、どうしたらいいんだろうね」
肩をすくめて苦笑した彼は、わたしたちの気持ちを配慮しているかのように、冗談めかした顔をつくった。
「空軍の知り合いに頼んでマリコをテキサスまで送り届けてもらおうかな」
緒斗は「そいつは最高のアイデアだな」と笑った。するとジェームズは「ま、おれはだいじょうぶさ。テキサスの土さえ踏めば、また、いつものおれにもどれるから」と鼻先で笑ったきり、黙りこくってしまい、サンフランシスコ国際空港に到着してからも、目を伏せたまま、背中をこちらに向け、別れのことばもかけずに、他の乗客にまじってキャビンを出ていった。

入国審査を終え、ベルトの上から自分たちのスーツケースを取りあげ、税関検査を受けて、ようやくロビーに出たとき、大きなダッフルを肩にかけたジェームズが、さっそうとした足取りでこちらへ向かってきた。
「たしか、YokoとOttoは、ホテルの予約、してなかったんだよね」
「だから、今から、バークレー市のホテルに、片っぱしから電話をかけようと思ってたところなんだ」
「おれ、マリコと過ごすはずのホテルには泊まりたくないから、予約をゆずってあげるよ。電話の使い方、わかるかい?」
「やってみれば、なんとかなるかも」とわたし。
「おれがあそこに並んでる公衆電話から、このホテルに電話をしてやるから、何も心配しなくていい」
「ええっ? でも、ジェームズはどこに泊るの?」
「サンフランシスコに海兵隊の仲間がいるから、そこに転がりこむよ。金もかからなくていいし。酒をもっていくから夕食にもありつけるはずだ」
わたしたちの反応をうかがうこともせず、沖縄からやってきた黒人青年は、足早に公衆電話の列へ向かい、すばやく受話器をとった。
そんな長身の彼の背中を追いかけるようにして、わたしたちはスーツケースを引きずりながら、ようやくジェームズに追いついた。
彼はわたしたちのラストネームをたずね、ホテル側とかけあい、そのおかげで、はじめて訪れたアメリカでの初日の夜のベッドは、あっけなく確保することができた。
お礼を述べようとしたら、彼はそのローストコーヒーのように光沢のある黒い肌に白い歯をのぞかせて「グッド・ラック」とだけ言い、大股で去った。

私たちはタクシーをひろい、ホテルの名前と住所の書かれたメモ用紙を運転手にさしだした。
ジェームズの手書きの英語は、まるで教科書からコピーしたもののように、おどろくほど繊細で流麗だった。

初めて乗ったイエローキャブの座席はヴィニールの臭いがきつかった。
運転手は、大きな音量でラジオを鳴らしながら、サンフランシスコのダウンタウンをめざして、怖くなるほどのスピードで飛ばし、高速道路は滑走路のように広かった。
すでに暗かったし、近くに大きな街がないためか、光のない殺伐とした風景しか目に入らなかった。
窓を開け放っていたので、強い風に頬をたたかれていたが、その乾燥した風と空気の匂いはまったく異国のものだった。
そのとき、すでに引き返すことのできる地点は超えてしまったのだと、ぼんやり感じていた。

そのうち海が近づいてきて、遠くには黒い低い山影が見えはじめた。
風に翻弄される髪にあおられるようにして、わたしの鼓動はどんどん速くなってきた。
そのとき、とつぜん、夜闇の向こうに、サンフランシスコの街明かりが、ぼうっと、まるで幻の都市のようにあらわれたのだ。
わたしは小さな驚きの声をもらしたかもしれない。
未知の世界への不安と期待のふたつが胸の奥でぶつかりあっていた。
けれども、なにげなく盗み見た緒斗の横顔にもおなじような緊張のこわばりを感じとったとき、ふいに母国がそこにあるような気がして、わたしはひとり(だいじょうぶ。なんとかなる)と思ったことを、いまでもおぼえている。
わたしたちが故郷なのだ。
どこにいても、あなたがいるかぎり、そこに日本はある。
そんな思いのはざまに、ベルボトムのジーンズをはいた、あの長身のジェームズの後ろ姿が、いつまでも、残像のように風景に重なったまま、ともに窓の外を流れていった。

1980年 6月24日 / サンフランシスコ
無断引用および無断転載はお断りいたします
All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko
All Rights Reserved.